10月18日
「太陽王」ルイ14世は「朕(ちん)は国家なり」と言ったと、昔世界史で習った。ウソである。フランス人のルイ14世が朕なんて言うはずはない。本当は何と言ったのか。調べてみるとどうやら“L’État, c’est moi”と言ったらしい。直訳すると「国家、それは私だ」となろうか。意味するところは同じでも、だいぶニュアンスが違う。
この間、妻と話している時、「おれ」と自称していることに気づいてハッとした。ずっと「ぼく」で通していたつもりだったからである。いつから「おれ」になったのだろう。勤めていた頃はシチュエーションによって「ぼく」と「わたし(またはわたくし)」を使い分けていたはず。仕事をやめ、さらにこのコロナ禍で、妻以外とほとんど会話をしない日々を過ごすうちに「おれ」になってしまったらしい。「おれ」には尊大な響きがあるようだし、注意しなければ。
英語なら「I」フランス語なら「Je」ドイツ語なら「Ich」という具合に、一人称単数の代名詞が一つしかない言語は多い。一方「朕」はまあ極端としても、日本語には自分を表す人代名詞が山ほどある。ぼく、おれ、わたしの他にも自分、小生、うち、わし、おいら、吾輩、拙者、余…。枚挙にいとまがない。立場や役職を表す言葉を代名詞の代わりにすることもある。母親が我が子に向かって「ママはね…」と言ったり、教師が児童に「先生は」と言ったりするのがそれだ。言語社会学者の鈴木孝夫(1926~2021)によれば、ある成人男性は、上司に対する時には「わたくし」、同僚には「ぼく」、大学の後輩には「おれ」、家で子供たちに対しては「お父さん」と言っていた。つまり、日本語では、相手が誰で、自分とどのような関係があるかがわからないと自称の言葉が決められないのだ。彼はこれを「相手依存の自己規定」と名付けた。
この、「相手に合わせて自分を規定しながら生きている」という感覚は、小説家の平野啓一郎が提唱する「分人主義」ともつながる考え方ではないだろうか。分人主義とは、「本当の自分」は一つではなく、対人関係や環境ごとに異なる人格が存在しているとして、それを「分人」と名付ける。そしてそのすべての分人が複合したものが「本当の自分」なのだという考え方らしい。なかなか卓見だと思う。生きづらさを抱えている人は、その生きづらさをもたらすのがどの分人かを見つけることが出来れば、それをゼロにはできなくとも、構成比率を下げることで「生き易く」なるというわけだ。
様々な代名詞を駆使しながら周囲との距離を測っていた日本人は、もともとそれが出来ていたのでないだろうか。近代になり、個人(individual)や自己同一性(identity)という、外来の考え方が定着したために、生きづらさを抱える人が多くなったのだとしたら皮肉なことだ。
一人称単数の代名詞を一つしか持たない西欧の人々は、一個の分かち難い存在としての自分が、神と直接契約を結んで生きていると考えている。今回のコロナ禍で、日本とは二けた違う死者が出ているのにマスクをしない人々や、痛ましい事件が続発しても銃規制に反対する人々、さらにはウクライナ紛争への対応などを見ても、(少なくとも)僕とは死に対する心構えが全く違うように感じた。その背景に宗教(それも一神教)の存在があるように思えてならないのだ。これについては、もう少し考えを深める必要があるだろうか。
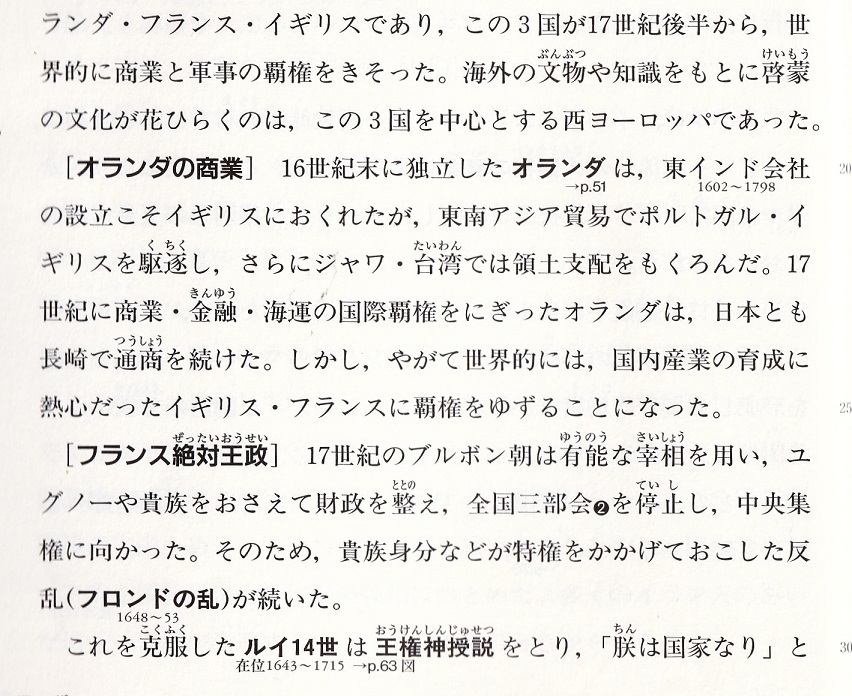


コメント