5月15日
ずいぶん前のことになってしまったが、5月2日に日本テレビ系で放映された宮崎駿の「君たちはどう生きるか」を録画しておいたものを見た。CMをすべてカットして2時間3分55秒。公式データには124分とあるから、まずノーカットと考えていいのだろう。
白状すると、僕はアニメ映画を見るのが苦手である。30分くらい見続けるのが限度で、それ以上になると神経が疲れてじっとしていられなくなるのだ。僕がTVのアニメを定期的に見ていた最後は「めぞん一刻」だからもう40年も前だし、一回分の正味は23分ぐらいだ。当時は画も粗いし背景はほぼ動かなかった。ジブリ作品でも、実は全部を通して鑑賞したことがあるのは「天空の城ラピュタ」だけで、それ以外はつまみ食い的にしか見ていない。今回はBDにダビングしたものをPCで何回かに分けて観た。おそらく正しい鑑賞の仕方ではないのだろうが。
見終わって驚いたことが一つある。この作品は封切り当時「難解」という評が多かったように記憶しているのだが、難解どころか単純極まりない作品だったのである。早い話が「主人公の真人が異世界に行って戻ってくる話」である。難解と感じた人は、この映画から何らかのメッセージを受け取ろうとして、それが見つけられなかったのだろう。「君たちはどう生きるか」というタイトルもミスリードな気がする。
冒頭の火事場シーンから、輪タクに乗って夏子が登場するあたりまでは息をするのも忘れている感じだった。その後の日本家屋や洋館のディテールも素晴らしい。だが、ここで登場する「ばあやたち」が揃いも揃って異形なのにまず辟易してしまう。宮崎アニメにはこうした異形の存在が多いとはいえ、この映画の彼らは妖怪ではなく普通の人間なのだ。それが極端にデフォルメされており、夏子や真人の四倍から六倍ぐらい顔が大きかったりする。また、真人の父が大慌てで帰って来る場面では、父の運転するダットサンが、「カリオストロの城」のカーチェイスを思わせるような有り得ない動きをする。実はこれらも僕のアニメアレルギーの原因の一つなのだ。あまり共感してはもらえないのだが、ディズニーランドやシーのパレードやショーでも同じようなことを感じる。細部まで作り込まれた精巧なセットの中心でなぜネズミやガチョウの着ぐるみが踊っているのか。それが僕にはどうにも居心地が悪い。それと似た感じである。
だから、サギ男のように最初から異類であればそれほど気にはならないし、異世界である塔の中ならそれでも良いのである(池から大量の鯉やヒキガエルが出てくる場面は気持ち悪かったが)。
塔の中は行方不明になった真人の大伯父が、隕石の力を借りて作った精神世界で、時の回廊で現実世界とつながっている。年老いた大伯父は自分の後継者として真人を呼び寄せたのだ。どうして夏子が先にこの世界に入ってしまったのかは説明されていないが、真人を呼ぶための罠だと考えれば一応の説明はつく。だが、産屋に入るのを「禁忌」というあたりも含めて、苦しいつじつま合わせの域を出ていない感じがする。
いずれにせよ、真人は大伯父の「豊かで平和な美しい世界を作りなさい」という誘いを断って、「殺し合い、奪い合う、愚かな世界」に戻って、「友達を作る」という道を選ぶ。ここでタイトルの「君たちはどう生きるか」が回収されるのだが、この「寓話」に悲しいほど説得力がない。
本編に戦争が描かれていないせいもあろう。真人の母が病院の火事で亡くなったのは「戦争の三年目」で、これは空襲ではない。真人が屋敷に行く途中で遭遇する出征兵士の見送り風景が、唯一戦争のリアルを感じさせる描写だ。真人の父はいっそ清々しいほどの絵に描いたような俗物だが、軍需産業で潤っている。真人もその父と、戦闘機の風防を美しいと感じる感性は共有している。お屋敷での食事を「おいしくない」という真人は飢餓体験とは無縁だろうし、二年後のラストでも父親はパージされてはいないようだ。
そもそも、吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」自体が、恵まれた階層の子弟を読者に想定したなんとも「ぬるい」本なのだ(「一億総中流という時代」2022・2・23投稿参照)。問われるべきは塔を出た真人のこれからの生き方なのだが、それは仄めかされさえしない。全くの肩透かしである。つまりこの映画は難解なのではなく、解釈が必要な(読み取るべき)内容がそもそも皆無なのだ。
とは言ってももちろん美しい映像には魅了された。今回はヘッドフォンで試聴したのだが、音響設計も素晴らしいと感じた。日常から離れた楽しい経験であったことは確かだ。
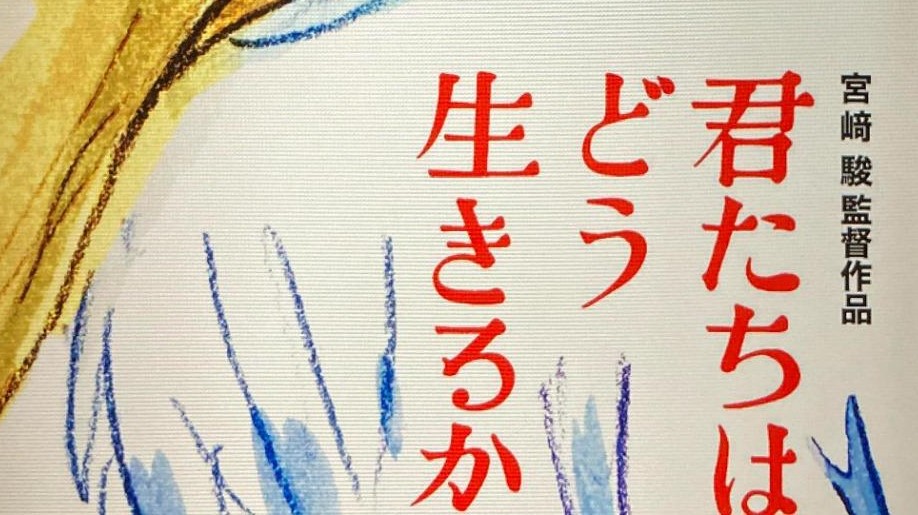


コメント