12月28日
(終始ネタバレです)日本映画専門チャンネルで岩井俊二監督の「路上のルカ」を見た。以前、ドラマ愛好家の畏友Hが紹介してくれていたので、いつか見てみたいとは思っていた。全10回で5時間半、三夜連続で深夜に放送していたものを録画して、三回に分けて昼間に見た。「キリエのうた」という映画を再編集したものだそうだが、僕はその「キリエのうた」を見ていない。キリエとかルカとか、キリスト教と関係があるのかと漠然と思っただけ、何の予備知識もないし、主演のアイナ・ジ・エンドのことも全く知らない状態で見始めた。最初女性の声でオフコースの「さよなら」が歌われる。たどたどしく、何の感情も感じられない歌だ。雪原を二人の人物が歩いている。「路上のルカ」とタイトルが出て、次に2011年の大阪。古墳のそばでザリガニ釣りに興じていた男の子たちが、何も話さない不思議な女の子に会って「イワン」と名付ける。ストリートミュージシャンの男性が弾き語りをする場面、これが長い。そのうちに画面右から黄色いレインコートに赤いランドセルの女の子が現れる。ゆっくり時間をかけて画面を横切り、フレームアウトする。つぎのカットでは、女の子はベンチに座っている。あの「イワン」である。彼女はじっと男性の歌を聴いていたが手招きされて男性の隣に座る。その後で教会に行き、炊き出しのカレーを食べるが、ここでもボランティアの女性の問いかけには何も答えない。小学校の女性教諭・風美(黒木華)はイワンの噂を聞いて古墳に行き、女の子を見かけるが見失ってしまう。その夜、木の上から女の子の歌声が聞こえている。別の日、例のストリートミュージシャンの所にイワンがやって来て、今度は一緒に歌う。見物人が増え、投げ銭が集まる。だが、ミュージシャンの男性は通報を受けた警官に連行されてしまい、イワンは逃げる。教会の礼拝堂に行き、天井を見上げて「アー」と声を出す。目に涙をいっぱいに溜めた少女の顔のアップで第一話が終わる。一編の映像詩である。イワンを演じた女の子(矢山花)がとにかく印象的だ。
さてここで僕は痛恨の(?)ミスを犯してしまう。第二話を飛ばして第三話を先に見てしまったのだ。このドラマは全十話すべて雪原で「さよなら」を歌う場面から始まることもあり、飛ばしたことに気付かなかった。第三話はアイナ・ジ・エンド演ずる高校生の希(きりえ)が、古びた日本家屋にやって来るところから始まる。家には夏彦(松村北斗)が待っていた。夏彦はウイークリーマンションのようなところに一人で住んでいて、家庭教師がついている。夏彦は高校三年生で、地元の大学の医学部を受けることになっていたが、一つ年下の希を妊娠させてしまうのだ。希に言われて彼女の家に行くと、大勢がクリスマスを祝っていた。希の父は亡くなっていて、クリスチャンである母は希が子供を産むことを許すという。希の妹のルカは第一話に出てきた女の子で、意外に野太い声で「異邦人」を歌う。その後、成績がスランプになった夏彦は逃げるように大阪の医大を受け、合格するとそれまで避けていた希に久しぶりに電話する。ここで「第三話」と出て、初めて第二話を飛ばしていたことに気付いたのだった。その第二話。風美が「イワン」を保護、小塚ルカと言う名前と石巻出身であることを突き止め、さらにルカの姉の希を探す夏彦のネットの書き込みを見つけて連絡する。そして夏彦が大阪にやって来てそれまでのいきさつを話すという展開になる。制作者の意図とは違うが、怪我の功名か、この順番で見たのは正解だったように思った。何よりこの作品について何の予備知識もなかった僕は、ここでようやく2011年の意味に気付き、夏彦がキリエの家に行くために乗った郊外電車は仙石線だったのかと今さらながらに気付いたのだった。第三話の冒頭に出てきた古い家は夏彦の祖父の家で、その祖父が亡くなった新盆の場面から回想が始まる。この場面が何とも言えずいいのだ。夏彦が伯父に地球は丸いと聞かされた瞬間に「物心がついた」という話や、伯父のパートナーの男性が「幽霊を召還する『お盆』は、よく考えると怖い」というと、夏彦の祖父と祖母の幽霊が一瞬現れるところなどが特に秀逸だ。江口洋介演じる伯父の「高尚な俗物」の感じが何とも魅力的で、この場面だけで退場してしまったのが惜しい。
結局夏彦は希の妊娠について自分の親には言えないまま、「あの日」を迎える。夏彦に電話するため、希が授業をサボって自転車で海辺を走る映像が美しい。そしてあの震災がやってくる。安易な設定であるのは確かだが、自分の弱さと卑怯さを自覚しながら、それでも誠実であろうとする夏彦を演じる松村がとにかく良い。後半に出てくる、同じように弱くて卑怯で、とても醜悪な中年男のナミダメとはえらい違いだ。そして、この第四話までの緊張感は紛れもない傑作だと思う。
それが第五話あたりから失速する。いや、広瀬すず演じる真緒里が初登場する帯広編はそれでもまだいい。真緒里がイッコになってからの東京編ではイッコをはじめとする登場人物の実在感が薄い。例えば豊原功補演じる元恋人などはいかにも一時代前の感じ。現実感がまるでないのだ。真緒里がイッコになる経緯が全く語られていないせいもあるが、どうもそれだけではない気もするのだ。
キリエ=ルカの歌声に惹かれて集まってくる音楽仲間たちは、誰も彼女のバックボーンを知ろうとしないし、彼女が路上生活者であることも(多分)知らない。いくら個の領域に立ち入らないのがある意味「都会の優しさ」であるとしても、これは不自然だろう。北村有起哉演じる音楽プロデューサーにしても、もし彼女が震災孤児であることを知れば、プロモーションに使おうとするはずだが、そうはならない。これでは第四話までの分厚い背景が全く生きてこない。そして最後の音楽ライブの場面が無駄に長い。
後半で唯一の見どころは、キリエ=ルカと夏彦の再会の場面だ。ここは美しかった。夏彦はルカに希を重ね、同時にルカは希の代わりにはならないことを改めて思い知らされたはずだ。しかし三十歳になっているはずの夏彦の今が語られることはない。
ドラマは最後に高校時代のルカが雪原を真緒里と歩き、「さよなら」を歌う回想場面になる。各回の冒頭より長く、ここでは初めて「さよなら」と叫ぶサビまで流れる。それまでの訥々とした歌い方から突如として攻撃的なシャウトに変わる。時系列で言えばこれが、真緒里=イッコがルカの歌を聴いた最初なのだ。彼女はルカに「歌は人の人生を変えるものでしょ」と言ったが、それはこの時の経験を指したものだったようだ。だが、この歌が彼女をどう変えたのかまではわからない。そして、キリエ(というかアイナ・ジ・エンド)の歌が人の人生を変えるようなものだとは僕には思えない。最初に冒頭で流れる「さよなら」が「たどたどしく、何の感情も感じられない」と書いた。その彼女の歌は途中でスイッチが入ったように別物になる。その声はほとんど暴力と言ってもいい。彼女の声に比べれば、路上ライブで「マリーゴールド」を共演した女の子の声の方がはるかに「癒やし」の声だし、音程も余程安定していた。キリエの歌は人のために歌われるのではなく、彼女が生きるために、闘うために歌われるものだからだろう。それは彼女が時折見せるダンスも同じ。彼女は歌い続け、踊り続けなくては生きられないのだ。だから、彼女はプロになろうなどとは考えないし、ネットカフェでシャワーだけ浴びて、電車で眠る生活をこれからも続けていくのだろう。
毎回のエンドタイトル、キリエが電車に乗っている場面(と歌)はこれだけで一編の映像詩だし、優秀なMVだと思う。さらに付け足せばすべての登場人物の中で最も魅力的だったのは、幼少期のルカを演じた矢山花で、この子のこんな表情を引き出せるだけでも岩井俊二という人は異能者だと改めて思う。
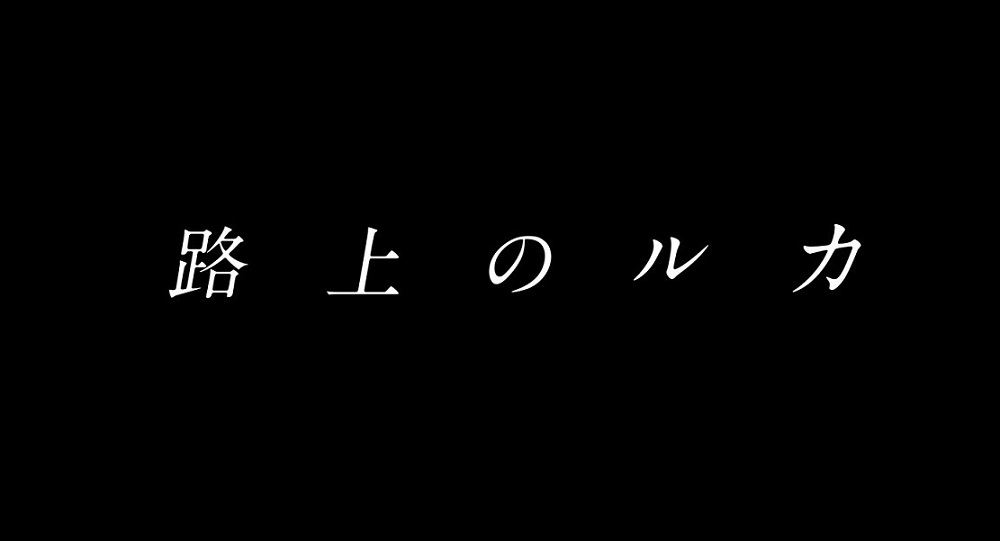


コメント