2月20日
朝日新聞に連載中の小説「あおぞら」(作・柚木麻子)は、1950年代の東京が舞台だ。具体的には1952年から始まって現在は56年に入っている。シングルマザーの村瀬立子が周囲の女性たちと手を携えながら、まだ珍しかった保育園の設立に尽力するという話なのだが、協力者の女性たちもそれぞれ葛藤を抱えながら、問題意識に目覚め、それを克服してゆく成長物語でもある。例えば魚屋のおかみさんである弥生は、第五福竜丸事件以来魚が売れなくなった騒動をきっかけに、反水爆運動にかかわってゆく。この第五福竜丸事件のあった1954年と翌55年のヴォリュームが今までのところ一番多い。
ここに描かれた時代は、1961年生まれの僕にとっても直接は知らない時代だ。著者の柚木麻子にとっては生まれる30年近くも前のことになる。なぜ作者はこの時代を描こうと思ったのだろう。
それを考える前にさっそく脱線。1954年と55年というのは、僕が愛する作品たちの舞台となっている時代である。
まず、僕が戦後日本文学の一つの頂点を示す作品だと思っている福永武彦の「死の島」。この作品は1954(昭和29)年の1月23日からその翌日を「現在」とし、その300日前からの(つまり53年からの)回想が随時挿入される形をとっている。この日を選んだ理由について作者は「この日はめずらしく東京に大雪のあった日」だからと述べている。また、作中では劇作家の加藤道夫の自殺(1953・12・22)が言及されている。
川端康成の「東京の人」(この作品については22・1・31に投稿した)は、54年の5月5日から、55年の6月2日までの物語である。作中には第五福竜丸の他、洞爺丸の事故等も触れられている。
日本ミステリー界の三大奇書の一つ、中井英夫の「虚無への供物」は54年の12月10日から翌55年が舞台となっている。この作品にはスタートから洞爺丸事故が影を落としている。殺人事件の舞台となる氷沼家の当主が洞爺丸の被害者なのだ。
さらに、前回も触れたばかりの横溝正史の「悪魔の手毬唄」(この作品も2022.1・21~26に投稿した)。1955(昭和30年)夏の物語である。この作品の時代背景については、かつて「高度成長のとば口という時期だろう。戦後の混乱は収まり、社会全体に明るさが見えてきて、一方、地方には昔ながらの習俗が残っている」(22・1・21投稿)と書いている。因習や旧弊を捨てた新時代の若者たちが生き生きと描かれているのがこの作品の特徴であり、魅力なのだ。
このように50年代の半ばごろというのは、僕が偏愛する多くの作品の舞台となった僕にとっての憧れの時代なのだ。高度成長期、一億総中流の時代に向かう一歩手前の頃である。だが、その頃が古き良き時代だったように感じるのは、その後の日本が70年間戦争に巻き込まれることがなかったことを知った上で振り返っているからということもあるだろう。この時代を現に生きていた人たちは核戦争の恐怖を今よりはずっと身近に感じていたはずだ。「死の島」の一日は、相馬鼎が水爆投下後の荒廃した光景を見た悪夢から目覚めるところから始まる。「東京の人」にも、核戦争への恐れは語られている。高校生の弓子の友だちの美代子の父が「もし戦争になったら、原子爆弾がこわいから、すぐに、(ヘリコプターで)日本アルプスの奥にでも、逃げ出そう」と語ったというエピソード等が語られる。
1954年は映画「ゴジラ」が公開された年でもある。もともとゴジラは古代の恐竜が水爆実験の放射能で巨大化したという設定で、第五福竜丸事件を受けて制作されたものだ。
ここで「あおぞら」に戻る。僕は柚木麻子の作品としては、「BUTTER」と「ナイルパーチの女子会」を過去に読んでいる。これらに登場する女性たちはみな痛々しいまでに真面目で、何か正体の分からぬ者たちとたたかっているという印象だった。それに比べて、「あおぞら」の村瀬立子たちがたたかっている相手ははっきりしている。今日(2月20日)の掲載分で、立子を妊娠させて捨てた男の母親である病院長夫人が立子のことを「不衛生な貧民施設にこの子を放り込んで、自分は好き勝手に学校だなんだと遊びまわっているの。そもそもは、子を中絶しようとした、母親としての情がない女」だ等と言い放つ。この院長夫人は、社会運動に目覚めた弥生から、「あんた方はあの戦争から何も学んでいないんだね」と糾弾されていた。
「不衛生な貧民施設」というのは、当時まだ珍しかった保育園のことだ。当時は、保育所に子どもを預けて母親が働くことへの公然とした非難があった。小説ではある男性の言葉として、「そもそも、母は家庭に帰れというのは、そんなにおかしいことなんですか? 普通のことでしょう。(中略)そもそも母親の務めとは子を産み、夫に仕え、家を守ることでしょう。普通のことじゃないですか。(中略)多くのまともな大人ならそう思っているし、そうあるべきでしょう」
今からは隔世の感のある言葉だと僕は思っていたのだが、昨今ではSNSなどでこれと似た主張を目にすることが多くなった。「一周まわって」ということなのか。「リベラルは有事に弱い」などという主張を見るにつけて、本当に有事になってもう一度痛い目を見ない限り、こういう人たちは目を覚まさないのかと思ってしまう。
今はまさに「バックラッシュ」の時代なのだ。女性の社会進出に否定的な主張をする政党さえ出てきている。こんな時代だからこそ1950年代に思いを馳せ、ここに描かれた立子たち先達の思いを辿ることの意義は、確かにあるのだと思う。
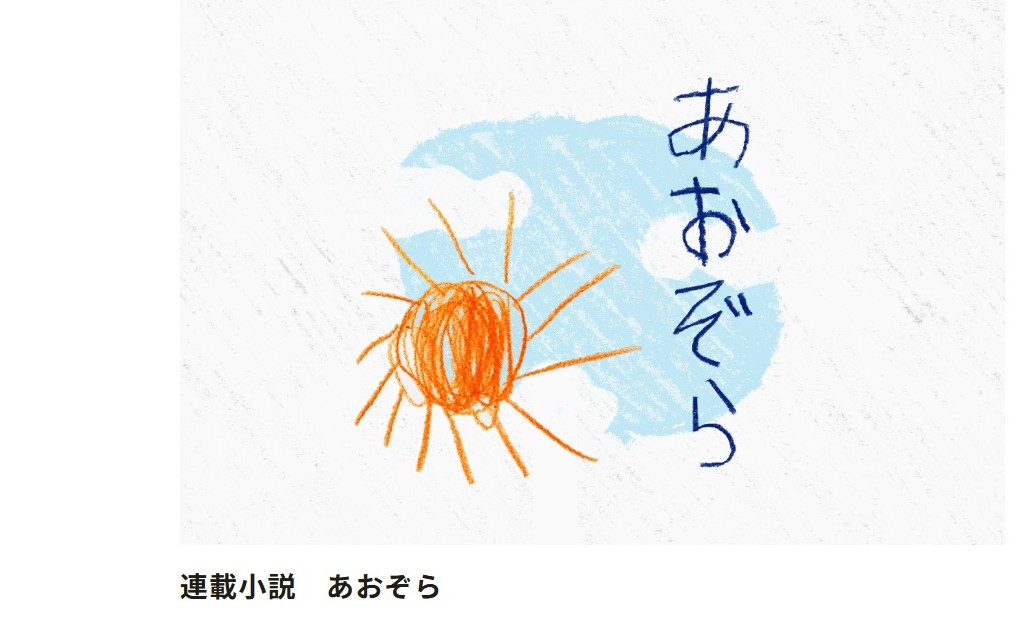

コメント