3月6日
堀江敏幸の小説、例えば「河岸忘日抄」等を読んでいると、目はページの上をたゆたい、夢うつつのようになってふと気づけば同じ個所を二度も三度も読んでいる。読み進めてから、ここは昨日も読んでいたことに気づいたりもする。僕は本に線を引かない主義で、それは本を汚したくないからでもあるが、次に読んだ時に先入観を持ちたくないためでもある。おまけにスピンというしおりの紐(この名は佐藤正午の小説で知ったが、和製英語らしい)を挟んでおくのも忘れることが多いので、なかなか先に進まない。所謂「タイパ」が悪いことこの上ないが、タイパを重視するならそもそも堀江敏幸など読むべきではない。ほとんどストーリーらしいものもないのだからダイジェストのしようもない(これは勿論ほめているので、僕はこの作家が大分好きだ)。
こういう文章をAIは書けるのだろうかと思った。そしてすぐ書けるに違いないと思い直した。必要な資料を読み込ませ、適切なコマンドを与えさえすれば(それがどういうものか僕にはわからないが)きっと書けるのだろう。
こんなことを考えたのは、最近新聞やTVで「チャットGPT」なるものが話題になっているからである。
少し前の天声人語で、ショートショートの名手、星新一の名を冠した文学賞で優秀賞を取った作者が、現実にAIを創作の一部に取り入れていたことが紹介されていた。天声人語子が喝采を送った「何でもいいから、楽をしたい。それは創作活動に対する心構えの欠如だ」という小説の中のセリフも、実はAIの力を借りて書いたものだったという「オチ」まで付いていた。
TVのニュースショーなどで紹介されている、チャットGPTの受け答えはもう少し優等生的で面白みがないが、学習させる資料や、問いの仕方を工夫すればもっと「個性的」な返答になるのだろう。書かれたものの個性は単語の選択によるとすれば、単なる偶然を優れて個性的と感じてしまうことはあり得る。
原稿用紙に万年筆で書く作家がほとんどいなくなったように、将来的にこういうツールを創作に使っていく方向になる流れは止められないだろう。一方でAIが完全に人間を凌駕するとは思わない。生活上必要がなくなっても、人間の表現したい欲求はなくならないから。それに、AIは知識をため込むことはできても追体験はできない。例えば情報として「渋柿」を知ってはいても、実際に甘柿と思い込んでかぶりついたのが渋柿だった時の、衝撃と落胆、後悔を感じることはAIにはできないのである。
個性について、最初に紹介した堀江敏幸の小説で語られている部分を引用、紹介してこの項を閉じることにする。
「言葉は、誰だって出来合いのものを学ぶんですよ、それこそ小学校の教科書に載っているようなものをね。辞書を引けば、意味が載ってる。でも、その出来合いの言葉を、どんな状況でどんなふうに用いるかによって、無限の個性が生まれるんです。ただし、組み合わせた結果がどんなに面白くても、なぜそうなったかについては説明がつかないんですよ。* つまり、とそこで彼が口をはさむ。分解はできても、もう一度組み立てなおすことのできないのが、そのひとの個性ってことかな」(新潮文庫版 110~111ページ)。
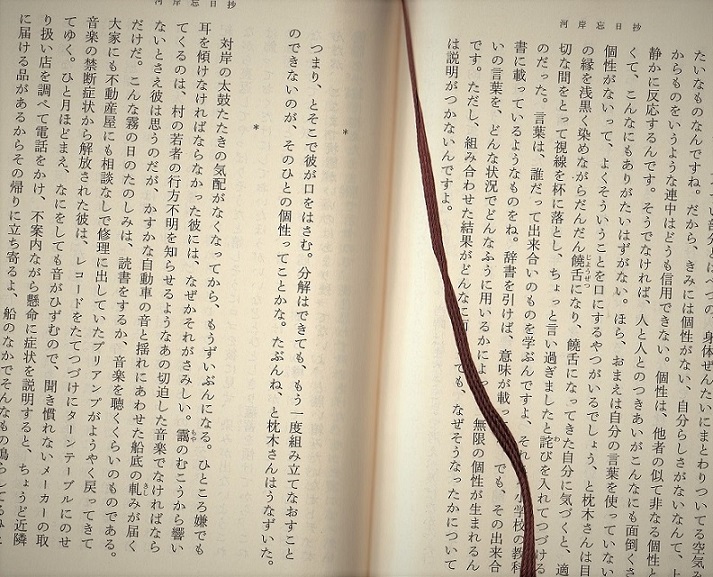


コメント