
12月2日
「宿命」と聞くと、頭の中に菅野光亮作曲のピアノ協奏曲が鳴り響き、海辺を歩く遍路姿の二人が浮かぶ。そんなことを思いながらページを繰ると、いきなり「『宿命ってなにかしら?』『生まれてきたこと、生きているということかもしれない』~映画『砂の器』(松本清張原作・野村芳太郎監督より)」とあった。この著者は僕とほぼ同世代である。
11月30日の朝日「天声人語」で新語「親ガチャ」と絡めてこの、土井隆義の論考を紹介しているのを読み、畏友Hからも薦められていたことを思い出し、岩波ブックレット「『宿命』を生きる若者たち」を手に取った。Hは現役の大学教員である。今の若者たちを前にして、モヤモヤとした、本当に君はそれでいいのかと言いたくなるような気持ち(当然、僕にも覚えがある)にかられることも多いと推察する。こうした論考などを手掛かりに少しでも彼らのおかれた状況を理解したいと思っているのだろう。
「親ガチャ」という言葉があること自体は知っていた。そんなことあたり前で、生まれる場所も時代も選べない(♪生まれた時が悪いのか~という昭和の歌謡曲があったっけ)のだ。だがそこに、格差を許容し、『人生を縛るものではなく、安定感を与えてくれるもの』と捉えるという恐るべきロジックが隠されているなどとは思いもしなかった。
最初に断っておくが、僕は社会学と聞くと眉に唾をつけたくなる人間である。様々なグラフを切り取ってそこから「知見」を得るというが、どこを抽出するか、どこに着目するかで全く変わってくるだろう。そもそもその調査の信頼性は何処まで担保されているのか。さらに、当初は「○○は✕✕であると考えられる」程度であったものが、次の段階では立論の大前提になっていたりもする…。
だが、この本に書かれていることはおおむねその通りではないかと感じた。自らの教員経験に照らしても、思い当たることが多いからだ。例えば「努力しない」生徒を嘆く同僚が多い中、僕は必要な時に必要な努力ができるということは立派な「能力」であり、それが欠けている生徒が増えていることをつとに感じていた。
僕は三十代の前半と四十代の後半の二回(90年代半ばと00年代終わりごろ)、俗に底辺校とか指導困難校とか呼ばれる(ヒドい言葉だが)学校で生活指導を担当したことがある。どちらも大変な経験だったが、90年代に相手にしていた彼らは、学校という体制を背負っている僕に対して、ギラギラした敵意を隠さず、徒党を組んで組織的に反抗した。それに比べて00年代はよほどくみしやすかった。僕はそれを自分の指導力が上がったためだと思っていたのだが、この著者によれば「社会の高原化」によって、若者が大人世代に反旗を翻すことがほとんどなくなったからだというのだ。なるほどね。
ここで僕自身(1961年生)のことを語っておこう。僕の父の最終学歴は高等小学校、母は尋常小学校、今でいえば中卒と小卒だ。一億総中流と言われた時代、我が家はその中の下と言ったところか。それを意識させられたのは小三の夏休み明けだった。この日関東地方の小学生は、夏休みに大阪万博に行った(行けた)子と、行か(行け)なかった子に二分された。後者だった僕は改めて社会の中での我が家の位置を知った(今にして思えば、必ずしも経済的な事情だけで行けなかったわけではないのだが)。我が家は豊かではなかったが、給食費が払えないとか、修学旅行に行けないということもなく、必要なものが買えないということもなかった。バイトする高校生は当時少なかったから、僕が初めてバイトをしたのは大学生になってからだった。その意味では、社会を知らずに大人になったと言っても過言ではない。
時代の気分を良く表している歌がある。かまやつひろしの「どうにかなるさ」(山上路夫作詞・1970年)。「今夜の夜汽車で/旅立つ俺だよ/あてなどないけど/どうにかなるさ/あり金はたいて/切符を買ったよ/これからどうしよう/どうにかなるさ」。僕の青春時代は、こういう歌が流行るようなある意味牧歌的な時代だったのだと思う。
今の若者たちをとりまく状況は全く違う。既に同世代のエリート候補生たちは、幼稚園からお受験等で選別されている。自分は早くからバイト等で社会に触れている。その上未来は現在と地続きだから、親を見ていれば自分の未来も想像がつく。当てもなく、金もないのに「どうにかなるさ」なんてうそぶいていられるような時代ではない。未来に過大な希望を持たない方が幸せだというのも仕方ない。
畏友Hのモヤモヤは僕も共有する。どうすればいいのか僕にはわからない。だが、突破するもしないも結局彼ら次第だ。僕らの世代にはなかったソーシャルメディアという道具もある。期待するより他はないではないか。
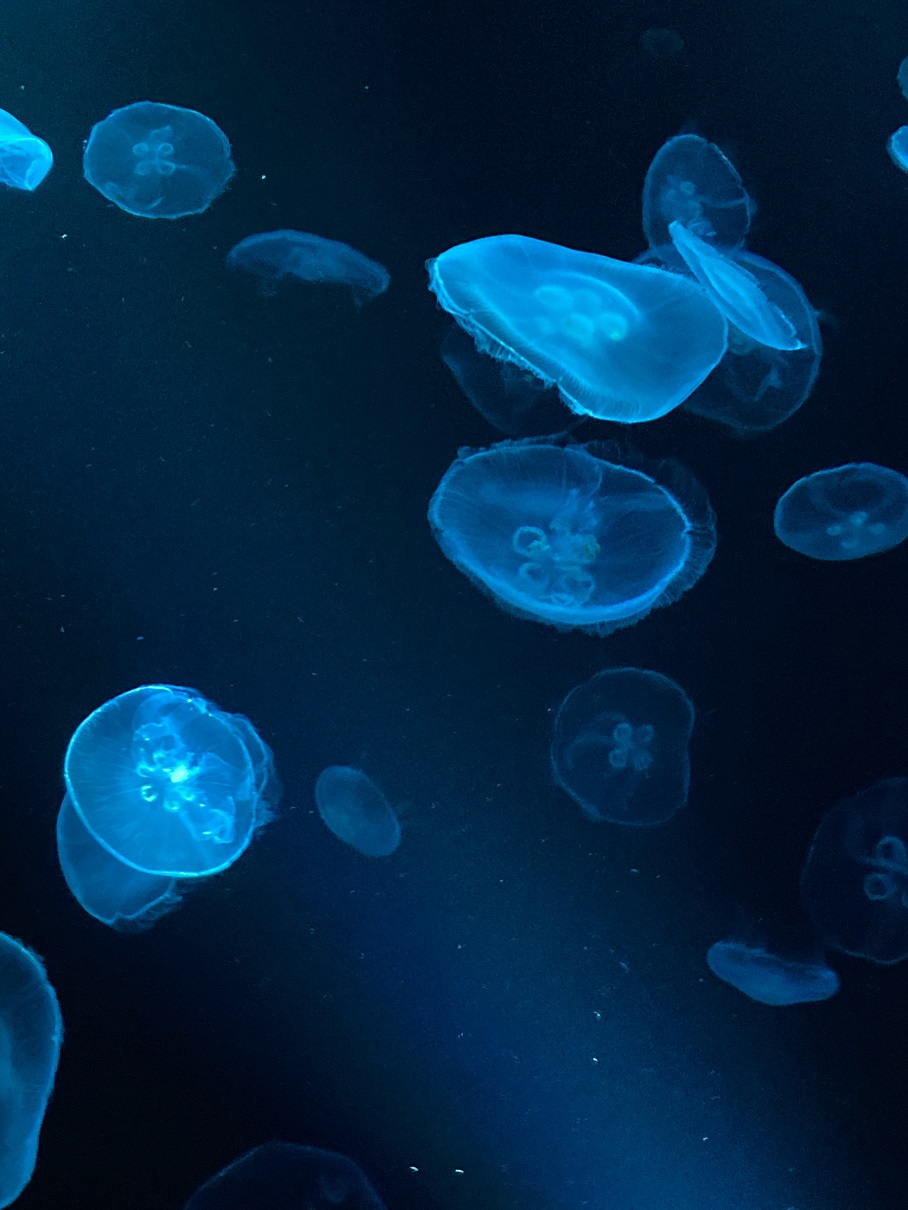

コメント