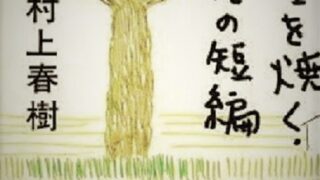 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 小説の愉しみ
7月7日 村上春樹のごく初期の短編に「納屋を焼く」という作品がある。こんな話だ(ネタバレ)。「僕」はひとまわり近く若い「彼女」と知り合いの結婚パーティーで会い、仲良くなった。具体的には書かれていないが、この「仲良く」にはもちろん性的な意味も...
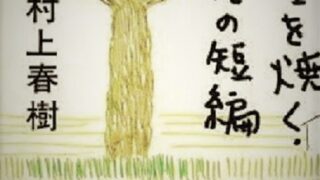 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学  詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 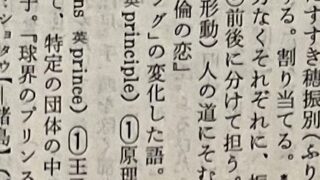 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学  詩、ことば、文学
詩、ことば、文学  詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 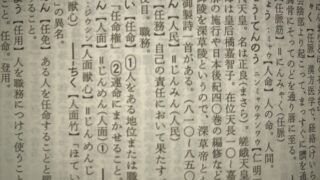 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 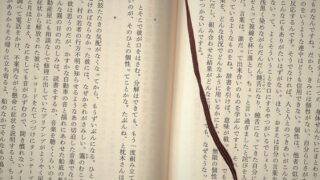 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 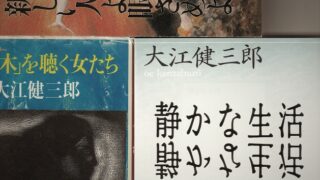 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 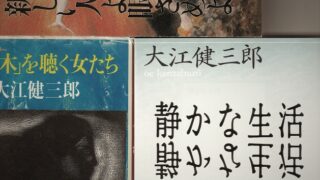 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学 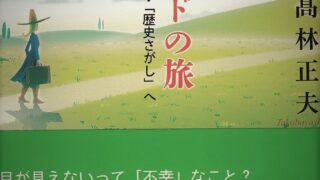 詩、ことば、文学
詩、ことば、文学